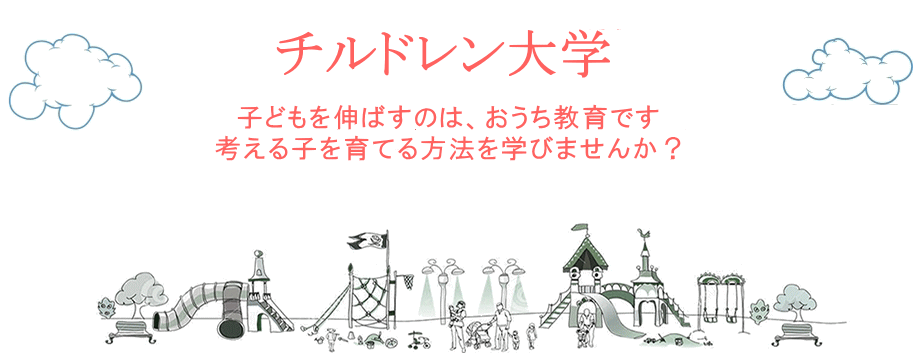我慢について考える

なんだか寒い・・と思って、ふと考えたこと。
『我慢』について
今の子どもたちは昔の子どもに比べて、我慢をしなくていい環境で生活していますよね。
昔、うちのおばあちゃんがよく言っていました。「今の人たちは何の苦労もしなくていい」と。その頃から更に4,50年経った今、子どもたちは・・・
暑さ寒さを我慢する必要がなく、お腹がすいて我慢するということもなく、重い物を持ってたくさん歩かなければいけない、ことなどあまりなく、ぬくぬく何も我慢せずに生きられる。
ちなみに我慢することと、学校の成績の関係について考えたことあります?
我慢ができる子どもの方が、ティーンになってから受ける、SATという全国テストの点数がいい!なんていうアメリカの調査結果があるくらい、我慢は重要みたいです。
でも、そんな研究がなくても、普通に考えたら分かりますよね。
ところがあーた、巷では我慢も努力もしてないのに、やたらと子どもを褒めることがいいと推奨されていたり、日常生活で(我慢しなくていいんだよね~)っていう無意識が、子どもの中に埋め込まれてしまっていたら、一体どうなるのでしょう。
そこで、我慢させることで、ここを押さえておいて欲しいというツボについてお話させてください。すっごくシンプルです。
あ、その前に、逆のことを考えてみます。
我慢できない子を育てるにはどうしたらいいか?
日常生活での例です。
- お腹すいたらご飯の時間じゃなくても食べ物を与える
- 欲しい物をすぐに与える
- やりたくないと言ったら、やらなくてはいけないことでも、親は一応文句はいつつ、最後は折れて、やらないことを許す
- 食べたいものだけ食べさせて、食べたくないものはほっておく
などなど
上記は我慢できない子どもを育てるのに、とっても効果的な方法だと思います。
では、我慢の練習のちょっとしたツボについて、思ったことをシェアさせてください。
是非、ここを押さえて欲しい!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
精神的な苦痛を与えて我慢させるのではなく、
我慢は身体的な行動を通じて教える
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
例えば、寂しかったり不安な気持ちを我慢させるとか、精神的な苦痛を慢性的に我慢させるのは、どう考えてもいい方向とは思えないですよね。
でも、健全に身体的に我慢させることなら、心が曲がらずに我慢することを学べると思えません?
- 雨が降ってて寒いけど、頑張って傘持って歩く
- お母さんの買い物の荷物を重いけど持ってもらって歩く
なんていう、日常のちょっとしたことですね。
ちなみに私の最近の身体的な我慢は「水風呂」。冷たいを通り越して、痛いです。